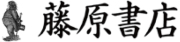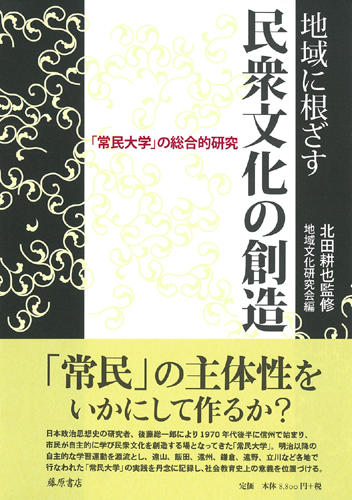- 北田耕也 監修
- 地域文化研究会 編
- A5上製 576頁 カラー口絵4頁
ISBN-13: 9784865780956
刊行日: 2016/10
「常民」の主体性をいかにして作るか?
日本政治思想史の研究者、後藤総一郎により1970年代後半に信州で始まり、市民が自主的に学び民衆文化を創造する場となってきた「常民大学」。明治以降の自主的な学習運動を源流とし、遠山、飯田、遠州、鎌倉、遠野、立川など各地で行なわれた「常民大学」の実践を丹念に記録し、社会教育史上の意義を位置づける。
目次
第一部 「常民大学」前史――地域住民・共同学習文化活動の伝統
A 戦前
第一章 徳富猪一郎の「大江義塾」 杉浦ちなみ
第二章 新井奥邃の「謙和舎」 胡子裕道
第三章 「研成義塾」と「自由大学」考――「感化」を手掛かりとして 石川修一
第四章 山本鼎「自由画教育」運動と金井正らの「農民美術」運動 東海林照一(追記・山﨑功)
第五章 東京・多摩における民衆の学習・文化運動 山﨑功
B 戦後
第六章 木村素衞の表現論と長野における社会教育実践 新藤浩伸
第七章 中井正一の「地方文化運動」と青年たち 新藤浩伸
第八章 戦後改革期における信州妻籠公民館による社会教育活動 上田幸夫
第九章 三枝博音「鎌倉アカデミア」の発足と展開そして今 飯塚哲子
第一〇章 信濃生産大学と農村青年の自己教育 田所祐史
第一一章 山形農民文学懇話会『地下水』の農民文学運動 相馬直美
第二部 「常民大学」の軌跡
A 総論
第一章 「常民大学」考 北田耕也
第一節 おとなの学び――その理念
第二節 「常民大学」の思想と展開――「飯田歴史大学」第一期完 了に寄せて
第三節 野の学びの二五年――成果と課題
第二章 「常民大学」への序奏――「寺小屋」から「常民大学」へ 小田富英
第三章 後藤総一郎論 杉本仁
第四章 「常民大学」の出版活動と後藤総一郎 久保田宏
B 各論
第五章 遠山常民大学 胡子裕道
第六章 飯田柳田国男研究会 杉浦ちなみ
第七章 遠州常民文化談話会 穂積健児
第八章 鎌倉柳田学舎 堀本暁洋
第九章 於波良岐常民学舎 山﨑功
第一〇章 遠野常民大学――『遠野物語』をめぐる遠野市民の「自己認識」の形成 佐藤一子
第一一章 立川柳田国男を読む会 田所祐史
第一二章 妻有学舎――新潟県十日町市の常民大学 穂積健児
第一三章 合同研究会 小田富英
C 補論
第一四章 柳田国男研究会 新藤浩伸
第一五章 茅ヶ崎常民学舎を辿る 松本順子
第三部 戦後社会教育における「常民大学」運動の位置
第一章 合同討議 主題をめぐる二、三の問題 地域文化研究会
第二章 総 括 戦後日本における民衆の学習文化運動と「常民大学」の位置 草野滋之
あとがき (新藤浩伸)
後藤総一郎著作一覧 (飯澤文夫・村松玄太)
後藤総一郎略年譜 (飯澤文夫・村松玄太)
執筆者一覧
A 戦前
第一章 徳富猪一郎の「大江義塾」 杉浦ちなみ
第二章 新井奥邃の「謙和舎」 胡子裕道
第三章 「研成義塾」と「自由大学」考――「感化」を手掛かりとして 石川修一
第四章 山本鼎「自由画教育」運動と金井正らの「農民美術」運動 東海林照一(追記・山﨑功)
第五章 東京・多摩における民衆の学習・文化運動 山﨑功
B 戦後
第六章 木村素衞の表現論と長野における社会教育実践 新藤浩伸
第七章 中井正一の「地方文化運動」と青年たち 新藤浩伸
第八章 戦後改革期における信州妻籠公民館による社会教育活動 上田幸夫
第九章 三枝博音「鎌倉アカデミア」の発足と展開そして今 飯塚哲子
第一〇章 信濃生産大学と農村青年の自己教育 田所祐史
第一一章 山形農民文学懇話会『地下水』の農民文学運動 相馬直美
第二部 「常民大学」の軌跡
A 総論
第一章 「常民大学」考 北田耕也
第一節 おとなの学び――その理念
第二節 「常民大学」の思想と展開――「飯田歴史大学」第一期完 了に寄せて
第三節 野の学びの二五年――成果と課題
第二章 「常民大学」への序奏――「寺小屋」から「常民大学」へ 小田富英
第三章 後藤総一郎論 杉本仁
第四章 「常民大学」の出版活動と後藤総一郎 久保田宏
B 各論
第五章 遠山常民大学 胡子裕道
第六章 飯田柳田国男研究会 杉浦ちなみ
第七章 遠州常民文化談話会 穂積健児
第八章 鎌倉柳田学舎 堀本暁洋
第九章 於波良岐常民学舎 山﨑功
第一〇章 遠野常民大学――『遠野物語』をめぐる遠野市民の「自己認識」の形成 佐藤一子
第一一章 立川柳田国男を読む会 田所祐史
第一二章 妻有学舎――新潟県十日町市の常民大学 穂積健児
第一三章 合同研究会 小田富英
C 補論
第一四章 柳田国男研究会 新藤浩伸
第一五章 茅ヶ崎常民学舎を辿る 松本順子
第三部 戦後社会教育における「常民大学」運動の位置
第一章 合同討議 主題をめぐる二、三の問題 地域文化研究会
第二章 総 括 戦後日本における民衆の学習文化運動と「常民大学」の位置 草野滋之
あとがき (新藤浩伸)
後藤総一郎著作一覧 (飯澤文夫・村松玄太)
後藤総一郎略年譜 (飯澤文夫・村松玄太)
執筆者一覧
関連情報
■「常民大学」とは、日本政治思想史の研究者である後藤総一郎を指導者として、一九七〇年代後半に、後藤の故郷である信州・遠山郷で発足し、現在に至るまで全国各地で息長く自主的な学習を継続してきた地域に根ざした市民の学びである。
■後藤総一郎は、「常民」を歴史主体であると同時に「批判概念」であると規定し、常民大学運動は出発した。常民大学とは、生活者が権力や「公」に対して批判精神を持ち続けながら「主体性」を確立するための運動体であった。
■後藤総一郎は、「常民」を歴史主体であると同時に「批判概念」であると規定し、常民大学運動は出発した。常民大学とは、生活者が権力や「公」に対して批判精神を持ち続けながら「主体性」を確立するための運動体であった。
著者紹介
【「常民大学」の創設者】
●後藤総一郎(ごとう・そういちろう)
1933年、長野県下伊那郡和田組合村遠山郷(現飯田市)生まれ。長野県飯田東高等学校(現飯田高等学校)卒業。明治大学法学部入学後、同大学政治経済学部に転部し、橋川文三に師事。東京教育大学講師、明治大学政治経済学部助教授を経て、1987年同教授。同図書館長、理事等を歴任し、在職中の2003年死去。
政治思想史と柳田国男研究をクロスさせた「民俗思想史」の新分野を拓く。市民講座「寺小屋教室」講師を皮切りに、「柳田国男研究会」、全国の「常民大学」を主宰し、「生活者の学び」を提唱した。
著書に『常民の思想――民衆思想史への視角』(風媒社)『遠山物語 ――ムラの思想史』(信濃毎日新聞社、後にちくま学芸文庫)『柳田国男論』(恒文社)『神のかよい路――天竜水系の世界観』(淡交社)ほか多数。『柳田國男全集』(筑摩書房より刊行中)編集委員を務める。)
【監修者】
●北田耕也(きただ・こうや)
1928年、福岡県小倉市に生まれる。旧制・佐賀高等学校、武蔵高等学校を経て、東京大学教育学部(社会教育専攻)卒。東洋大学社会学部教授、明治大学文学部教授を経て、明治大学名誉教授。
おもな著書に『大衆文化を超えて――民衆文化の創造と社会教育』(国土社)『明治社会教育思想史研究』(学文社)『近代日本 少年少女感情史考』(未來社)『「痴愚天国」幻視行――近藤益雄の生涯』(国土社)『〈長詩〉遥かな「戦後教育」――けなげさの記憶のために』(未來社)『下天の内』『一塵四記 下天の内 第二部』(藤原書店)等がある。
*ここに掲載する略歴は本書刊行時のものです
●後藤総一郎(ごとう・そういちろう)
1933年、長野県下伊那郡和田組合村遠山郷(現飯田市)生まれ。長野県飯田東高等学校(現飯田高等学校)卒業。明治大学法学部入学後、同大学政治経済学部に転部し、橋川文三に師事。東京教育大学講師、明治大学政治経済学部助教授を経て、1987年同教授。同図書館長、理事等を歴任し、在職中の2003年死去。
政治思想史と柳田国男研究をクロスさせた「民俗思想史」の新分野を拓く。市民講座「寺小屋教室」講師を皮切りに、「柳田国男研究会」、全国の「常民大学」を主宰し、「生活者の学び」を提唱した。
著書に『常民の思想――民衆思想史への視角』(風媒社)『遠山物語 ――ムラの思想史』(信濃毎日新聞社、後にちくま学芸文庫)『柳田国男論』(恒文社)『神のかよい路――天竜水系の世界観』(淡交社)ほか多数。『柳田國男全集』(筑摩書房より刊行中)編集委員を務める。)
【監修者】
●北田耕也(きただ・こうや)
1928年、福岡県小倉市に生まれる。旧制・佐賀高等学校、武蔵高等学校を経て、東京大学教育学部(社会教育専攻)卒。東洋大学社会学部教授、明治大学文学部教授を経て、明治大学名誉教授。
おもな著書に『大衆文化を超えて――民衆文化の創造と社会教育』(国土社)『明治社会教育思想史研究』(学文社)『近代日本 少年少女感情史考』(未來社)『「痴愚天国」幻視行――近藤益雄の生涯』(国土社)『〈長詩〉遥かな「戦後教育」――けなげさの記憶のために』(未來社)『下天の内』『一塵四記 下天の内 第二部』(藤原書店)等がある。
*ここに掲載する略歴は本書刊行時のものです
《訂正》
本書初刷290頁12行目に、誤記がございました。
読者、関係者の皆様に深くお詫び申し上げます。
地域文化研究会
(誤)総一郎は教員であった後藤忠人に養子として迎え入れられ、
(正)総一郎は教員であった父後藤忠人のもと、